|
|
阿満 利麿先生
|
自然法爾論は、運命論であったり、人為を排した自然や成行きを重視する人生論を決して意味してはいない。ましてや、すべてをそのままにうけいれるという、現状の絶対肯定論であるわけがない。 阿満利麿『法然の衝撃』
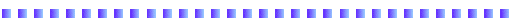
阿弥陀仏の誓願によって実現する凡夫の往生の様子が、「自然」であり、「法爾」なのである。(略)そこには、念仏者の処世術や、人生観のあり方は、どこにも説かれていない。(略) 問題は、従来の「自然法爾」論が、このような信者の主体的選択の道を閉ざす方向にはたらいてきたことであろう。つまり、阿 弥陀仏の誓願を信じることによって我が身の往生を確信し、なにものにもさえぎられることのない精神の自由を手にしたものが、現実社会でどのように生きてい くか。そこに生じる筈の主体的選択を、いままでの「自然法爾」論は、殺してきたのではないか。 阿満利麿『法然の衝撃』
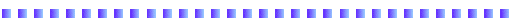
日本人は、法然の本願念仏によってはじめて、道徳、倫理など世俗の一切の価値から超越した、「宗教」というものを手にすることになったのである。(略)それまであいまいであった道徳と宗教の違いを明確にしたことである。本願念仏においては、本願を信じるかどうかだけが問われるのであり、それ以外のことは、一切問題とされることはない。 阿満利麿『法然の衝撃』
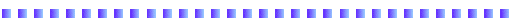
人間には、改悛したくても改悛できないような人間もいる。宗教の立場は、改悛できない人の、できない理由を認めるのであり、したがって、宗教の立場からいえば、死刑制度はあり得ない。 阿満利麿『生老病死の教育観』
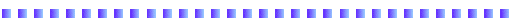
自然と一体感を得ることによって、さまざまな人生の危機や死の問題を超えていく道があるのではないかと申しましたが、それだけで超えていけるなら世の中の宗教は必要ではありません。 阿満利麿『生老病死の教育観』
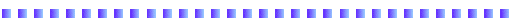
心理学やカウンセリングの心理療法で死の問題は超えられません。(略)現代という時代は、人間の悩み、不幸、苦しみ、不条理をカウンセリングが解決しようとします。有限の世界では手に負えない問題を、有限の世界の心の持ち方で解決しようとします。しかし、それはすぐに破綻することだと思います。 阿満利麿『生老病死の教育観』
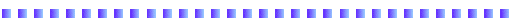
宗教家とは、常人とは異なる、特別の「霊力」の保持者だという先入観があるのです。そして、その「霊力」の源泉は、多くの場合、「苦行」にあります。宗教家とは、常人ができないような「苦行」を実践し、その結果、特別の「霊力」が身についている人のことだ、と考えられているのです。
卑近な例をあげれば、今日でも葬式に職業宗教家を招くのは、もっぱら彼らの力によって、死者の安楽を確保し、また、死がもたらすさまざまな災厄をあらかじめ封じ込めようという、無意識の期待がはたらいているからでしょう。
民衆のほうは、あくまでも、職業宗教家と「霊力」に期待しているのです。 阿満利麿『信に生きる 親鸞』
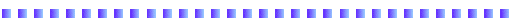
カリスマにひきいられる集団では、異質なものの考え方が生きていくことができません。 阿満利麿『宗教の力』
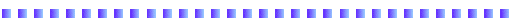
本来、無力感というのは念仏者の立場からはでてこないはずなのです。なぜなら、人が無力であるということはわかりきっているからです。その無力で非力な人間が、平和を願い続ける。そういう願いに生きることができる力をもらっていることこそ、他力の信心を得ている証拠ではないのか。
同朋の幸いのために行動する。その行動は、いつでも挫折と懺悔と敗北を結果するでしょう。しかし、そうなったとしても、また本願力を仰ぎ、再び勇気を奮い起こして立ちあがる。それでも、また挫折を繰り返す。どこまでもどこまでも、そうした挫折と再起との繰り返しでありましょうが、しかしそれこそが、我々凡夫の、「願いの捨て石」となって生きるすがたにほかなりません。 阿満利麿 『行動する仏教 エンゲイジド・ブッディズムの動き』
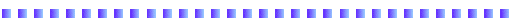
呪術とは、自己の欲望を投影するところに生じる。神仏に祈るといっても神仏にわが欲望の実現をせまっているだけだとしたら、それは呪術的行為といわねばならない。それに比べると、宗教とは、自己の否定の上に成立する。 阿満利麿『法然を読む』
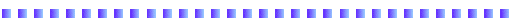
先祖たちが「輪廻」という考え方を受け入れたのは、ほかでもない、人間存在があまりにも不可解で不条理に満ちていたからではないだろうか。いったい人はどこから生まれてきてどこへ去っていくのか、一切確実なことは分からない。また卑近なことでいえば、たとえば、正直に一所懸命働いても、いつまでも貧困から免れることができないとか、あるいは、大悪人ほどこの世を栄耀栄華に生きるとか、人生には不条理があまりにも多すぎる。いったい、不条理に満ちたこの人生を、どのように納得すればよいのか。こうした思いに対して、「輪廻」は一つの回答を与えてきたのではないか。いかに荒唐無稽に見えようとも、「三世」や「輪廻」は、人間存在と人生の不条理や不可解さについての、一つの納得できる論理を提供してきたといえる。
つまり、「輪廻」の思想から学ぶべきは、そうした考え方を要請せねばならなかった人間存在の不安、人生の不条理という点なのであろう。
中世人は、「六道輪廻」といういわば神話、あるいは今風にいえば〈物語〉を媒介にして、人間のもつ根源的不安を克服したのである。 阿満利麿『法然を読む』
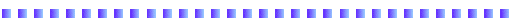
まず「自身」がどのような存在であるかを十分に吟味せよ、という。「自身」とは、罪悪を犯すことにおいて限りのない存在であり、そのゆえに生死を重ねること久しく、はるかな昔から輪廻に沈み、解脱はとても不可能な存在なのである。また「自身」とは、煩悩が満ち満ちた存在であり、道徳的な善や仏教が勧める善行の蓄積はきわめて少なく、そのために三界に流転し、迷妄の世界から脱出することができないでいる。
現実の自分は、煩悩と罪悪に満ちた存在でしかない。
「罪悪生死の凡夫」という自覚に立てば、自分のような人間はとても救われないという絶望に陥るしかない。どうしてこのような絶望が救済に結びつくというのか。
思えば、「凡夫」という自覚が深まれば深まるほど、普通は、とてもこのような自分が救われる道はもはや見いだせないという絶望に陥るだけであろう。そこでは、絶望からの救いは、まだ見いだせない。自覚だけでは、「凡夫」という状況は克服されないのだ。それでは、なにが足りないのか。「凡夫」である状況から抜け出たいという願いが必要なのである。「凡夫」であることの自覚に、さらに「凡夫」からの脱却を願う求めがくわわって、はじめて宗教的世界が開かれる。
「凡夫」の自覚が深まり、進退窮まって「凡夫」の救済が求められるとき、はじめて「凡夫」に注がれている阿弥陀仏の慈悲が実感できるのである。こうなると、「凡夫」であることは、絶望的状況にとどまらず、阿弥陀仏の慈悲のなかにすでに包まれているということになる。
自分が「罪悪生死の凡夫」であることが信じられたとき、おのずと、阿弥陀仏の本願が衆生の成仏を目標としていることに気づく。阿弥陀仏が「凡夫」を救うということが信じられるのは、自分が仏になる手段を一切断たれている「凡夫」だという認識が前提となるということだ。 阿満利麿『法然を読む』
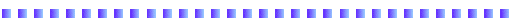
従来の仏教では「水火の難」という煩悩からの解放が目的であったが、善導や法然の浄土教では、煩悩のただなかにあって、しかも煩悩を超える道を提示したのである。煩悩の否定や克服は問題ではないのだ。文字通り「凡夫」のままで救われて行く道があるのである。だからこそ、煩悩まみれの生活を恐れる必要がないという。繰り返していえば、普通は宗教的信仰に生きる者は、煩悩から解放されているかのように考えられやすいが、善導や法然にあっては、煩悩のままで救われてゆくのである。 阿満利麿『法然を読む』
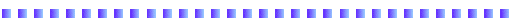
人間の固有性とは、法然の立場からいわしめれば、人々の背負っている業のなかにある。Aという人間が、BやCという人とは異なり、Zという人ともちがう固有の意味を有しているのは、Aが背負っている業が固有だからである。そして、その業を背負うのは、本人でしかない。
このような考え方においては、一つの価値を絶対視して、それをあらゆる人々に強制するということは生まれない。 阿満利麿『法然を読む』
|
|

