|
|
宮城 顗先生
|
自分の考えは絶対に間違いないという固執ほど世の中を暗くするものはありません。
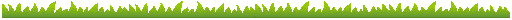
罪と自覚し、痛みと感ずるところに、人間であることが唯一保たれる。
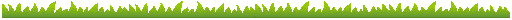
宮城顗『歎異抄講義』
信心したからといって、悲しみや苦しみが消えて楽に生きていけるという話ではございません。ただ、信心によって悲しみや苦しみが清められることがある。信心がないときには悲しみや苦しみが濁るのです。何によって濁るかというと、私がかわいいという思いで濁るのです。その時には、悲しみではなくて愚痴になる。何でこんな目に会わなければならないのか。何で私だけこんな目にと。

自分の苦しみにおいて人間の苦しみに出会っていく。自分だけが、と思っていたのが実はそうではなかった。苦しみや悲しみを受け止めていける場所があるとき、苦しみや悲しみは消えないのですけれど、その苦しみや悲しみが広く大きな世界に開かれていく扉になることがございます。
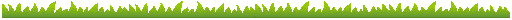
宮城顗『大無量寿経講義』
清浄ということは、一口で言えば、エゴが破られるということです。諸仏浄土を照見し、観ることによって、自分の体験・自分の知識などによってつくりあげていた自分の世界、執われ、固めていた自分の世界が自ずと破られていく。

聞法しようが念仏申そうが、悲しみや苦しみは消えはせんのですね。聞法し、念仏すれば悲しみや苦しみを味わわなくてすむかというとそんなことはない。ある意味で悲しみや苦しみをより深く体験するのでしょう。より深くということは個人の悲しみとか苦しみにとどまらない。

仏教はまず人間を行き詰まらせるのです。

本当に自分の弱さを深く知った人が、その弱さを悲しむ心において、ともに歩もうとする。

結局、死に切れなかったら愚痴と怨みしかのこらないんだな。

仏教においては、信心があろうと信じまいと、その人の死に方も、死んでからどうなるのかということも変わりはないのです。

年をとって自分の力に限界を知らされれば知らされるほど、逆に自分を生かしている世界がいかに大きいかを知る。

仏法に照らされなければ、穢土でもなければ苦悩でもないのです。不満とか腹立ちとか愚痴とか、そういうものはあるでしょうけれども、人間としての苦悩というものは出てこんのでしょう。本当に人間としての苦悩を知るということは、解決しえないものとして問題を受けとめる。そういうところに人間としての苦悩というものがあるわけです。どこまでも解決を夢みるかぎりは、腹立ちやら、愚痴やら、怒りやら、そういうものでしょう。

転悪成善というのは善悪の分別を転ずるのです。善悪の分別に苦しんでいる、その心を転じて徳と成すと。悪と徳は次元がちがうのです。(略)転ずるというのは、決して悪というものを悪でなくするということではない、逆に悪の自覚を与えるということです。罪を消し失わないのです。罪の自覚を開くのです。真に罪を懺悔する心は徳に生きる心ですね。

「省く」というのは、目に矢が突きささっている形ですね。ですから、しかと目にとめるという意味ですね。矢が突きささっているように、事実が目に突きささっている形ですね。ただ見ておるのじゃないのです。
目に突きささるのです。もう見てしまったのです。どれだけ目をそむけても消えないものとして苦悩の衆生を見ておるのです。大悲心というのは、苦悩の衆生が仏の心に突きささっているのでしょう。そのように苦悩の衆生によって仏の心が引き裂かれているのです。そこでは衆生の苦悩の重さと仏の大悲心とは等しいのです。

夢は実現してはじめて意味をもつのです。けれども同時に、実現するとともに消えてしまうものですね。夢が実現したら夢は必要ないのです。夢は実現したら消える。願は実現してはじめて力になるのでない。願が力を生みだしてくるのです。

人間は生き方に迷うておる存在ですね。他の動物には、おそらく生き方ということにおいて迷いはないのでしょう。いかに生きるか、どういう生き方をするか、ということは身体の本能が知っているわけですね。人間だけは、いかに生きるべきかということに迷うのです。

どんなものの中にも美しさを見出し、尊さを見出していくのが仏法の智慧なのです。

地獄と天上界というものが生きていることの意味を問う世界なのでしょう。地獄は悲惨さ、惨めさにおいてそれこそなんでこんな思いをしてまで生きなければならないのかと、何でこんなつらい思いをしてまで生きなければならんのかという、その悲惨さの故に意味を問うのでしょう。
天上界はいろいろの具体的な目標というものが全部満たされた世界ですね。満足した世界です。人間の欲望が人間の思いのごとくに満たされた世界が天上界ですね。ところが、そこにあらわれてくるものが、退屈の問題です。所在なさですね。天人五衰ということがあるわけです。衰というのは、生命感の衰退ですね。身の置きどころがない。そこにおることが虚しいのです。そこでは何のためにここにこうしておるのだろうという思いが出てくるわけです。地獄は悲惨さの故に意味を問いますが、天上界は逆にすべてが満たされた後の虚しさの故に意味を問うのでしょう。何のためだったのかと。

仏法というのは、生存の意味を尋ねる道だということがあるわけですね。生存の状態をよりよくするという道じゃない。

曽我先生が、「浄土は西岸にあるけれども、浄土の門は東岸にある」とおっしゃいますように、門は我々の生活の上に開かれるのです。

一切の存在を諸仏として見出してくる世界が、阿弥陀の世界だ。
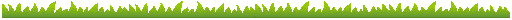
宮城顗『正信偈のこころ』
自分に対する夢というものは、どこまでいっても捨てられないものです。自分にもそのくらいはできる、自分も同じ状況にいたらちゃんとやっているさ、われとわが身に対する云いわけはかぎりなくつづきます。

人間は底なしに怠惰なるものであります。逆にいいますと、実際にはどれほどの努力もしたことがないからこそ、まだ、その気になりさえすれば自分にもできるのだという夢を夢みていられるのであります。身をもって実践しようとしたとき、実際にはなにほどのことができるか、自力のかぎりをつくした人にしてはじめて、自力無効の事実がいたくしらされるのであります。
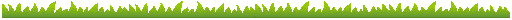
宮城顗『正信念仏偈講義』
本尊というのは単なる礼拝の対象ではないのです。自分が生きていくうえでのよりどころを表すわけです。

ほんとうのいちばん深い闇は、わかっているという思いです。なんでもわかったことにしてしまっている。(略)わかっているという思いは、そこにでんと腰を下ろすのですから、晴れるときがないのです。

なにごともなく、あたりまえのこととしている日々の生活の背後に無数の人がいる。私が一つのことを成し遂げられるということの背後には、無数の人がおられる。

人間の幸せ、幸福感というのは、感動するところにあるのです。ほんとうに心から感謝せずにおれない、そういう事実に会ったとき、人間はいちばん幸せを感じるということなのです。

仏というのはどこにましますか。仏によって目覚めたもののうえにあるのです。

曇鸞大師が明らかにされた還相というのは、苦悩の衆生に仏が学ぶのです。衆生の苦悩に学ぶ歩みです。

自分しか見ていないときにはなにをすべきかわからない。欲望をどこまで生きても、ほんとうに満足することはないのです。

親鸞聖人にあっては、償い切れるような罪は罪というに値しないとおっしゃるのでしょう。

罪業というのは、死んでおわびをするというようなものではない。死によっても終わらないものです。

死んだらそれで帳消しにしてもらえるというようなものではないのです。死んで罪を償うというのですけれども、仏教の智慧からいえば、死んで償えるようなものは罪というに値しないのでしょう。

貪欲を離れる、自己固執を離れるというのは自己固執しなくなることではなく、自己固執を一歩も出ないことを悲歎することなのです。

自らの在り方を深く悲歎するという心だけが人間としての心を回復していくのです。

慚愧というものの深さを親鸞聖人は悲歎ということばで述べておられるわけですが、その自らの在り方を深く悲しむという心がないとき人間関係が失われるのです。

慚愧がないとき、それはどこまでも自分の思いでしか出会っていないし、自分の都合のところでしか評価しない。

他の存在とのかかわりのほかに自己というものはない。他の存在とのかかわりを断ち切るときには、人は自己であることを失うのです。自己であることを失うということは、ただその人だけの観念の世界に、つまり自己満足の世界に閉じこもる。そういう自己満足の中に閉じこもって、他の存在に心を開かないのが、実は驕慢なのです。

衆生としての救いというのは、苦悩がなくなることではないのです。人間は苦悩しているがゆえに、苦悩がなくなれば救われると思うのですけれども、ただ苦悩がなくなったというだけならば、退屈というより深い問題がかならずそこに出てくるのです。人間の命は、苦悩がなくなっても満たされないものとして生きているのでしょう。逆に人間はともに苦しんでくれる人がいるかぎり、生きていけるのです。いのちは、だからこそともに苦しみ、ともに喜び、ともに悲しんでくれる人との出会いが開かれる世界を求めているのです。国土というものはそういう?会一処の世界、すべてのものがともに一ところに出会う場として願われているのです。

安田理深先生のことばでいえば、「仏道というのは向上の道ではない、向下の道だ」ということです。向上の道は能力によって差別ができるでしょう。理想を求めて向上していく。向上の世界ならば力あるものがより向上していける。

問題がなくなって喜べるのではない、問題を受け止め、生きていける道が見つかった、立つべき世界が見えた。そのことが歓喜なのです。現実を担っていけるということです。

ほんとうの自己とは、なんじ自身の内にある志願だということなのでしょう。信心を得るということは、自己の内なる志願を自覚せしめられることであり、賜ることなのです。

毎日の生き方は、やはり自己中心であって、生きているかぎり貪欲瞋恚はなくならない。けれども、ふとその自己を振り返って、そこに迷い悩むということが起こる。そういうものを与えられている。そしてそこに、ことばにはならなくても、人間としてほんとうに生きたいという願いを持ち、自己の生き方を尋ねるようになるのです。それが人間の志願なのです。志願というのは特別な心ではない、人間として自己をほんとうに生きたいという心です。ただ自我を主張して生きていくだけではない、人間としてということが深いところで促してくる、そういう心を持っているのです。

みんなに願われているものとしてのかけがえのない自分を見いだすということが、私はある意味で真宗なのだと思います。私の命は私のもの、もう一ついえば、あなたの命はあなたのものだぞ、あなたの責任だぞ、どうするのかということでしょう。一つの命を受け止めるということ、ほんとうに自分の命を自分の身において受け止める。しかもその私というものは、みんなにパチパチと拍手され、そしてまた私もみんなをパチパチと拍手するという、そういう共なる世界。

自分の賜っている命の尊さに気づかないとき、外にあるものを追い求めるのです。外にあるものをどれほど追い求めても、貧しさは消えない。

仏法の智慧を「忍」ということばで表すわけです。仏教において智慧というのは、いろいろなことを知っていることではない。事実を事実として受け止めていく勇気です。それがどんなにつらいことであろうと、どんなに厳しいことであろうと、それが事実であるならば、事実としてうなずいていくという勇気を表すのが忍ということばです。

智慧がないことを愚痴と表す。その愚痴というのは弱さです。愚痴というのは、わからないということではない。事実を事実として引き受けられない弱さです。

無我の我というのは、実体ということです。それでは実体というのはどういうことなのかということになるわけですが、仏教では、常、一、主宰なるものを我、実体というと定義します。永久に変わらず、それ自身だけの力で存在し成り立っている。そして自分のあり方は自分が決定できるという存在が実体なのです。ところが、この世におおよそ永久に変わらないものがあるか。それ自身だけの力で成り立っているものがあるか。自分のあり方を自分で決定できるものがあるかというと、そういうものは、なに一つありません。時とともに変わり、そしてやがてはなくなる。またすべてのものは相縁って生起しています。お互いに縁となり合って存在しているのであって、自分だけの力で、自分だけの都合で存在しているものはなに一つない。

いつまでも自分が存在し続けるかのごとくに固執している見方の中には、ほんとうに生を愛するということは、生まれてこないのです。

自力の生活というのは、自分が生きていることをあたりまえと考えるところから出発する生活です。それに対して、他力の生活というのは、そこに生かされてあることの不思議を感ずるところから出発する生活です。ですからそれは努力をしない生活ではなくて、努力において努力できることを喜ぶ生活です。自力の生活は自分のした努力を頼みにし、自分のした努力を誇る生活です。

他力というのは、けっして人の力をあてにする、寄生虫のような生き方、そういうものではありません。努力ということで申しますと、自力は自分の努力を誇る道です。わが力を頼みにする道です。それに対して他力は、努力できる自分を喜ぶ道なのです。(略)努力してもそれをわが努力として誇るのではなしに、かえって努力できることに大きな喜びを感ずるのでしょう。(略)それに対して自分の努力を誇る人は、その努力が人から正当に評価されなければ努力ができなくなるのです。

真の幸福というのはなんだろう。(略)一つは不変、つまり変わらない。(略)それからもう一つは、普遍、だれにでも平等に与えられているものでないとだめだということです。

本願というのは私を固めていくような願いではなくて、私を破る願いです。いままでの私がそこに捨てられて、新しい自分というものに目覚めていくような、そういう願いです。

弥陀の本願われを見捨てたまわずということを信ずるということです。

仏教は諸仏の世界、一仏ではないのです。仏というのは絶対的な存在ではない。一つの存在が絶対的になにか権力を振るう、そういう仏ではないのです。

釈尊が悟りを開かれたということは、人間は悟りを開くことのできる存在、人間は仏になる存在だということを明らかにしてくださったという意義があるのです。

救いというのは、どんな問題でもそれを担っていける場所と力とを賜るということでしょう。

私の人生を貫く一つのこと、そういうものが見つかる。自分にはっきりするということが実は救いということです。

親鸞聖人において問題なのは、教えの優劣ではないということです。この私に、その教えがいただけるのかいただけないのか。この私を救ってくださる教えはどこにあるのかということが問題なのです。

浅い心は人の苦悩を軽く扱うのです。だいたい浅い心ほど、人の苦悩をわかったようにいうのです。

信心は、罪から人を救うと同時に、人間の罪の深さを知らせるのです。つまり、信心の智慧において、はじめて見えてくる罪の深さというものがある。同時に、わが身の罪の深さを知らせてくる、その光というものにうなずかされていくのです。

目が覚めるためには目が覚める材料を持っていなければならない。なんにもない人が気づくわけにはいかない。そうすると、もがくしか手がない。つまり苦しむのです。そしてまた迷うのです。そして業をつくり、そして苦しむ。苦しんでまた迷う。

本願というのは、ことばを換えますと、人間としての根本の課題です。浄土とは、私が命ある限り果たしていくべき課題というものを賜る世界なのです。

自分を律することができると自負している人というものは、かならずどこかで弱い人を切り捨ててしまうのです。つまり、自分を律することのできた人だけの道になっているのです。

自分に自信をもっている、自分の心に迷うのです。

信心は仏を信ずる心ではなくて、仏の心をいただいた心です。

この人生全体を挙げて必至すべき確かな方向が明らかになる。同時につねにいまが喜べる。そういう人生を賜ったときが救いなのです。
。わが力になお夢をもち得る、もっていられるのは、ほんとうにその力を尽くしたことがないからなのです。

外道というのは、幸せという名目で人間の尊さというものを奪い取っていく道なのでしょう。

信心というものは、自分の人生に対する態度を決定するものです。

信心によって賜る喜びというものは、端的にはこの自己が喜べるということ。この私の人生が喜べるということです。

無常観というのは、頼りにならないものはきっぱりと頼らないという態度をあらわす。

ありがたいというのは、資格がない、あるはずがないということが、それにもかかわらず現にあるときに、ありがたいと感ずるのです。ですからありがたいという歓喜は、懺悔と讃嘆という二つを内容として持っているのです。してもらえるはずのない身という懺悔と、その身がいま現にしてもらっているという讃嘆とに生きる心が念仏です。

念仏というのは、自分の口で称える念仏ではなく、口から出る念仏なのだ。私が称える念仏ではなく、思わず私からこぼれ出るのが念仏なのだということです。

いつも問題を真っ正面から受け止めていくというのが宗教的偉人なのです。厳しく追い詰められることによって、深く求めていく人が宗教的偉人なのです。

願が成就することが救いではないのです。逆に願を持つことが救いなのです。願いが成就してはじめて得られる満足などというものはないのです。逆に自分の生死を尽くして生きられる願い、そういう自分の生死を尽くして担わずにはおれない願いというものが見つかることがほんとうの幸せなのです。

真宗では、罪福の信、現世の利益というものを否定します。なぜ求めないかというと、りっぱな信心を持っているから、現世の利益なんかでけっして惑わされないのだというような、そんなことではありません。そうではなく、逆に、現世の利益などで救われるような、そんな浅い苦悩ではないということがあるのです。ほんとうの苦悩を知らないから、現世の利益を祈っておられるのです。

私たちの生活を振り返ってみますと、どうも「また今度ね」というようなことばかりなのです。今がいま、このことをせずにおれないということが、ほんとうには見つかっていないということがあります。
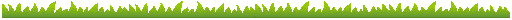
宮城顗『蓮如上人に学ぶ』
私の上におこってきた苦悩が消えてなくなることが救いではなく、そういう問題に出遭ったことを扉として、より大きな、確かな世界に目覚め、歩まされていくということが、救いでございます。救いとはゴールインしたことじゃないんです。初めて出発点に立てたということなんでしょう。

仮は具体的現実です。具体的ということは、いつか、どこか、誰かが、何かとして存在しているとき、具体的存在という。逆に言うと、その時、その場での、そのものにおける事実だと。決して、いつでも、どこでも、誰にでも、と直ちに言えない。普遍というときは、いつでも、どこでも、誰にでも、です。
仮の自覚を失うときに私たちは具体的な事柄を絶対化してしまう。これが偽です。私における事実をすべての事実として、絶対的な事実として立ててしまう、固執する。
仮は偽に変質するか、真をあきらかにするかです。

罪を消して善にするのではなく、「罪を消し失わず」ということは罪の意識の確保です。その自らの罪を深く悲しむ心だけが仏法を聞かしめる力となっている。自らの罪業深重であることに頭が下がっていく。そこにこそ聞き求める心が呼び覚まされてくる。ある意味で行き詰まりが聞になるわけです。

無生法忍の忍とは、勇気でございます。生ききり死んでゆける勇気です。仏教で忍とは、ものごとをはっきり理解している、認める、という意味です。
どんなにつらくともそれが事実であるならば、事実として耐え忍ぶという勇気。それが智慧ということです。智慧に対する愚痴は、受け止められない弱さでございます。自分の思いにすがりついて受け入れられない弱さです。

親の愛情といっても無条件の愛情ではない。親のものさしに合うときだけ喜んでくれる。ものさしに合わないと叱責され、尻をたたかれる。それで親が満足してくれるような仮面を子供はつける。
子供のためによかれと思っていても、それが条件から出発しているんなら、それは子供の心を開かない。どういう私が出てきても、それを受け止めてもらえるという時、はじめて安んずるという心が出てくるんでしょう。
初めから条件を突きつけて、これでなければ認めんぞということでは安んじないですね。条件に合わねば排除されるというのであれば、自分のためにしてくれてはいても、根本のところで安んずるということはできない。
しかし私の事実を事実として認めてくれる、どんな愚かさも、どんな迷いも、まずそれを事実として認めてくれる。そういう時に安心して心が開けてくるんです。

清浄とは単なる形容詞ではなく、清浄にしていくはたらきです。はたらきを抜きにして清浄という事実はない。つまりはたらきを持たないならば、我一人清浄なりという世界に陥るわけです。
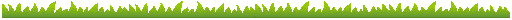
宮城顗『仏弟子群像』
真理は、それを問う問いのふかさに応じて、あらわになってくるのです。問いが仏法に新しい生命、新しい表現をよびおこしてくるのです。
聞いてすぐ納得する素直さも、それはそれで尊いことですが、そういう人たちばかりのときには、仏法は、聞いてすぐわかる人たちだけにしか伝わらなくなってしまいます。なかなか納得せず、どこまでも問いつづけ、ひたすら考え、そのようにしてはじめてうなずけた人は、それだけに、うなずけた教えをどんな人にも伝えることのできる言葉を身につけられます。

その人を失った悲しみの深さは、実はそのまま、生前その人から我が身が受けていた贈りものの大きさであったのです。かけがえのない大きなものを贈られていたからこそ、その人を失ったことが、深い悲しみとなって迫ってくるのです。

どれほど秀れた教えであろうと、教えを受ける人間の現実にそぐわぬときは、ただいたずらに、人を傷つけ、悩ますだけに終わり、結果として、法をもそこなうことになる。

神通力というのは、自分にできることとできないことをキッパリと見分ける力です。私たちは、できないことをいつまでも夢見つづけたり、できることをすぐにあきらめたり、一喜一憂をくりかえして、自分の命を本当に燃やしつくせずにいます。

生きている間私たちは、食べてこの身を養い、着てこの身を守っているのです。そして、食べているかぎり、動物であれ植物であれ、他の命を奪いつづけているわけです。他の命のおかげで、この身を保っているのです。してみれば、この身は、我が身であって我がものではないのです。他の命から賜ったものなのです。ですから、自分の肉体を大事にすることは、この身を養ってくださっているいろいろな命を大事にすることなのです。

どんなにすぐれた人が立派な悟りをひらいたとしても、その教法が説かれることによって、あらたに悟りをひらく人が生まれ出なければ、それは真実の教えといえない。その真理が人間の事実となって生きてはたらく力にならなければ、それは真実の教えとはいえないのです。

一つの教えに生きるとき、日々の体験のすべてが一つの方向に定まってゆくということがあるのです。だから、そこには必ず、生活、生き方の選びがおこるのです。けれども、それはけっして人間としての決断を意味しているのではありません。人間の誓い、人間の決断などというものはまことに頼りにならないものです。また同時に、自分の意志で、自分の分別で仏教を選びとったのなら、それは結局、自分の分別に依って生きているのであって、けっしてその教えに依って生きているものではないでしょう。態度決定させているものは個人の意志ではなく、遇い得た教法なのです。

釈尊は、個人的な能力を自負し、誇示するもの、あるいはまた、その個人の能力を讃嘆し、驚き敬伏するような人々をこそ、人間としての尊さを見失った愚かな者であることを教えられたのです。誰にもできないことができる超人になることではなく逆に、まわりの人々すべての、その人その人の尊さを讃えることのできる心豊かな人、我が身に賜っている命の尊さに頭の下がる人となることをこそ教えられたのです。

いつとはなしに積もってしまう塵とは、自分の体験のみを絶対的なこととして誇る自負心、驕慢心であります。どこからともなくにじみでてきて肌をおおってしまう垢とは、自分のしたことや考えについての執着心であります。その塵と垢とを払い除かないかぎり、努力すればするほど人をへだて差別し、軽蔑する人間になってゆくのです。人々への愛に生きているつもりが、いつしらず、愛に生きている自分自身への自己満足と自己固執にすりかわり、人々がその愛に生きる自分を理解しないときには、逆にその人々を軽蔑し、憎みさえしてしまいます。

耳なれ雀は、自分は聞いていると自負しているだけに、聞こうとさえしないものよりもなお一層始末が悪いものです。仏法を誤解させるのは、えてして、この耳なれ雀なのです。聞法することがあんな人間になることなら、私は御免だ、といわせるのです。

言葉は人間の生活にとって大事なものです。言葉が通じるということは心が通じるということ、お互いに人間として出会えたことを意味しています。そして人は、他人が何気なくもらした一言にふかく傷つくこともあれば、たまたま耳にした一言で救われることもあるのです。言葉を無神経に使っているときは、必ず、人間そのものを無神経に扱っているときです。
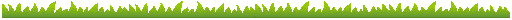
宮城顗『浄土論註・聞書寸言』
生物的にはあたりまえのことを、罪と自覚し、痛みと感ずるところに、人間であることが唯一保たれる、と言っていいかも知れません。

責任を外へ外へと求めていくひとには、出遇いも共感もありません。頷きあうということができない。

人間はお互いに他者を本当に理解するなどということはありえない、たとえ、親子、夫婦であろうとも、心底、理解しあうなどということはできないのだ。それなら、人間はまったくバラバラなままに生きるほかないのでしょうか…。人間はまったく他者と心を通わすことはできないままに終わるのでしょうか…。そうではありません。実は相手をほんとうには理解しえないことを、深く悲しむ心、その心だけが、どこまでも相手の心に寄りそい、相手の心に聞き取っていこうとするのだと思います。

人間の苦悩には、個人の苦悩ということはないんだと。苦悩はひとりひとりだけれども、そのひとだけの苦悩というものはないんだと。ひとりの人間は、命の事実として、社会という、時代という関わりのなかに、苦悩を受けとっているのです。

ひとりひとりの人間を大事にあつかうということは、その人のもっている苦悩を大事にあつかうということです。人間はそれぞれに、だれに代わってもらうことのできない苦悩をかかえて生きている。私どもにおいては、苦悩の事実から目をそむけて生きるということがございます。

現代生活において、私たちが失っている最大のもの、それが不可思議さを感ずる心だと思います。今、生きているということに不可思議さを感ずる心は、言いかえれば、今、現にこの身にたまわっているものに不可思議さを感ずるのです。
不可思議さという言葉を有難さという言葉におきかえてもいいでしょう。私たちは、今、現に、身に受けているものの有難さ、不可思議さを感ずる心を失ったままで、外に外にと、生き甲斐を求めているわけです。しかし、有難さを不思議さを感ずる心がないままに、いくら外に求めても、それはちょうど、底のないザルで水を掬おうとしているようなものです。今、現に身に受けているものをあたりまえと思う心ならば、新しくなにかを手に入れることができて、有頂天になったとしても、しばらくすれば、あることがあたりまえになってしまうからです。

自分のあり方に対する吟味がない。そしてただ、感覚があうかあわないかでよりわけていく。自分の感覚を疑わずに、逆に自分の感覚でよりわけていく。そして、その自分の感覚そのものを問うことがないこと、それは非常に恐ろしい関わりを生みだしていくのではないでしょうか。

自己中心に生きている時には、いっさいのものを利用するという関わりしかもてません。そこにおいては、自分の領域を広げれば広げるほど、それと比例して人間が孤独になり小さくなっていくという世界しか生きられない。

一番深い無明は、みんなわかっておるという、そういう思いとしてあるわけです。それは必ず、みずからを是とし、排除の姿勢をとらせる。

自分の領解を絶対化して疑うことのないのが邪見です。これが無明ということです。無明ということは、何も知らないということではない。わかっているという心が一番暗いのです。

謙虚というのは『広辞苑』に「あくまで柔順になろうとする心」とありますが、意味深いと思うのです。「なろうとする」というのは、まだなっていないということですから、「なろうとする」のです。つまり謙虚になろうとする心こそが謙虚さというものです。謙虚になったと自分で思ったら、実はそのときはもう謙虚ではなくなっているのです。それはちょうど、子供の気持を一番よく知っている、と思いこんでいる親が、実は一番子供の心から遠く離れており、子供の気持がわからないと悲しんでいる人のほうが、はるかに子供の気持に近くよりそっているのです。

悪知識を一口で言ってしまうと、私を眠らせ、私を安らかにしてくださるような善知識でございます。悪知識は、答えを与えてくださることにおいて、逆に問いを失わせるということであります。

仏道において、師といい友といい仏というのは、いうならば私を否定してくださる先生。私を否定することにおいて、私を目覚ましめ、私を破ってくださるものの前に身を引き据えるところに、初めて私自身を知らされるのでありましょう。よしよしと言ってくださる人の前では決して自分に目覚めるということはないことであります。

乱暴に申しますと、自利しかないのだということです。利他と言いましても、利他のための利他ということでおわりますなら、それはよく言えば自分を犠牲にして利他するという意味になりましょうし、悪く言えば、お節介をやくことにおわる。

一切の存在は存在すべき因縁(必然性)あって存在している。その因縁というものは、たまわるものであって、つくり出すというわけにはいかない。私の存在は私の恣意で成り立っているのではない。
私どもは、その因縁生を見ずに、自分のひとつの立場からあらゆるものに価値づけをする。そして無用なものは切り捨て、価値なきものは無視していく。

引き算というのは、あと何カ月、あと何日という、だんだん手持ちの時間の存在が消えていく。生きるということは、一日生きれば、一日引き算です。また一日が過ぎてしまったという。そういう引き算の行き先は、こんな私になってしもうて、という嘆きしかでてこない。
それに対して「引き算から足し算の変換」。つねに「今をもらって生きている」。これが「因縁生」。足し算の人生。その今というのはつねに出遇いたまわる一点です。
生から死への人生は引き算の人生、逆に死から生へという視点に開かれてくる人生というのは足し算の人生でしょう。

答えをもつということは、人間は答えに照らして理解するよりも、判定することに夢中になる。判定するということは、そこにレッテルをはるということです。

不安を感ずるというのは、いまの自分のあり方が本来じゃないという、その危うさの予感です。

仏道の具体的歩みということは、問題を解決することでなく、一切の事柄を、信仏の因縁に転じていくことに尽きる。
|
|

